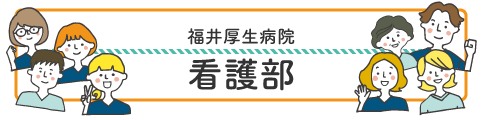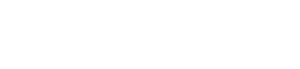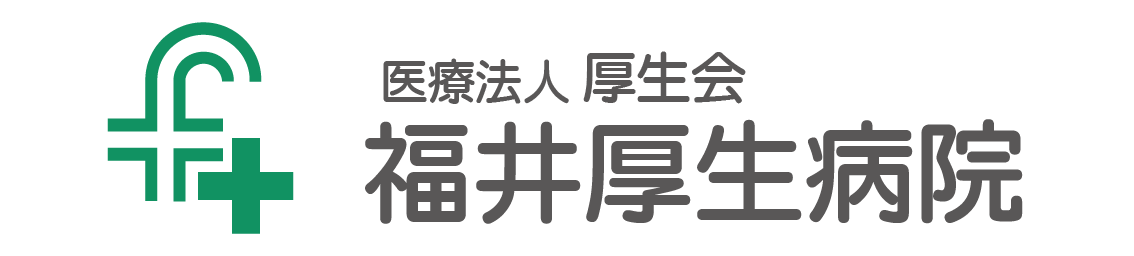0776-41-3377(代)
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
院内感染防止対策
院内感染防止対策
院内感染とは、広い意味では院内で発症した感染症を指しますが、普通はさまざまな病気を患っている患者さまが、病院で検査・治療・ケアなどを受けて感染症の病気にかかることを指し、患者さまだけではなく病院職員も感染を被ることがあります。
感染症は人体の内部に常在する微生物や、体外から進入した病原微生物から発症します。体内に侵入した微生物がすべて感染症を発症することはないですが、病原微生物と生体との関係で病気に進行します。抵抗力の弱い患者さまが多く集まる病院などの医療機関では、集団的に発症する危険性が高いため、院内感染対策を講じて院内発症を未然に防ぐ努力を行っています。
病院には院内感染防止対策として委員会の設置が義務付けられています。当院では1995年に院内感染防止対策委員会を発足させました。そこでは毎月各病棟における感染症の状況を、症状や各種検体からの細菌培養成績・ウイルス情報をもとに正確な把握をし、院内感染の予防および院内感染発生時の適切な対策を講じることを最大の目的としています。その目的を達成するべく、感染管理資格医師(Infection Control Doctor:略してICD)を中心とした実働チーム(Infection Control Team:略してICT)を設け、適宜病棟巡回を行っております。
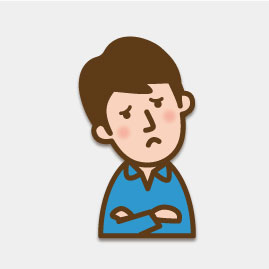
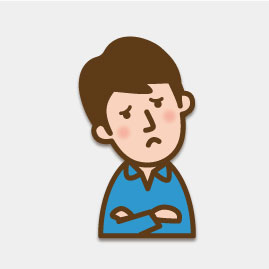
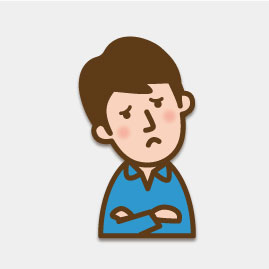
ICTってなんですか?



過失に基づくものばかりでなく不可抗力によるものも含め、医療が行われる院内感染防止対策委員会のもと実働的な活動を行なう院内感染対策チーム(Infection Control Team:インフェクションコントロールチーム)のことをいいます。
当院のICTは、感染管理認定医師を中心に看護師、薬剤師、臨床検査技師が協力し、互いの専門分野を活かしながらチームで患者さまや職員を感染から守る活動をしています。
ICTレポート
コロナ禍を経ての教訓
2022年2月




新型コロナウイルス(COVID-19)感染症は、2020年(令和2年)1月15日に国内で初の感染者が確認されてから急速に拡大し、3月には小・中学校、高等学校の臨時休業の要請、4月には「緊急事態宣言」が発出され、社会・経済活動は大きく制約されました。
そんななか医療機関では、刻々と変化していく感染状況に応じながら、感染拡大防止のための様々な対策や措置が講じられており、それは今でも続いています。
コロナ禍といわれる感染拡大予防に奮闘した期間を振り返り、ICTのコアメンバー薬剤課吉田さんから話を聞くことができました。
- 薬剤師として、コロナ禍で改めて実感したことは何ですか?
-
抗菌薬に限らず、比較的古くに承認された薬剤では最近の薬剤と違い、細かな薬物動態プロファイルや減量規定、増量幅、調節法、安全上の注意点が添付文書、インタビューフォーム、適正使用ガイドでは確認できないことが多々あります。
これらが分からない薬剤では有効性、安全性、そして特殊病態での投与を検討するためには Pubmed、Googlescholar などで検索し、過去の調査や最新の研究を調べると良い根拠が見つかり、診療録への記載も豊かになり、医師への説得力も増すんじゃないかと思います。
今回のように緊急事態下では、異例の速さで薬剤やワクチンが採用されることも少なくないと実感しました。そんな薬を扱ううえで薬の特性を確認しておくことも大切なことだと思います。 - 「薬を特性を確認しておく」とは具体的にどのように取り組むと良いと思いますか?
-
興味深い研究・調査もあるので「それらは一体どのような研究で、どういったことを著者らは言おうとしているのか」と日頃から教科書、成書で確認できない疑問は調べる癖をつけると良いと思います。
- 「確認できない疑問を調べる」ことで、コロナ禍のような非常事態でどんなことが大切になりますか?
-
コロナ禍では抗ウイルス薬やmRNAベースの新たなタイプのワクチンが開発されました。
これは米国の国立衛生研究所(NIH)には明確に記載されていましたが、国内の情報では不明な点が多々ありました。そのため、これらが承認に至った研究論文、NIHの情報を読んでみて、理由を知るようにし、薬剤師として院内の適正な使用に向けて情報発信をしてきました。
ソーシャルネットワークを使えば、より早く情報を知ることも出来ますが、マスコミのような表層理解にならないように文献検索を活用し、より根拠のある提案、診療録記載とすると良いと思いました。 - コロナ禍を経た薬剤師に期待されることは何だと思いますか?
-
痩せた小柄の高齢者、極度の肥満、他に特殊な解剖のある状態など、さまざまな患者さまへの最適投与量を各薬剤の薬物動態からの推測、また治療実績を調べ、提案・検討することなどが、コロナ禍を経た今後、ますます薬剤師に期待がかかることだと思われます。
ICTエンブレムの秘密
2013年11月22日


当院には約600名の人が働いています。その中でICTのメンバーだけがつけることができるこのエンブレム。ICT設立10周年を記念して、2013年の11月につくられました。
ICTとは感染症や感染対策を専門に活動する『院内感染対策実働チーム(インフェクションコントロールチーム)』のことです。
今回、エンブレムの発案者で福井厚生病院ICTイチ熱く、アグレッシブな薬剤師の吉田さんに直接、話を聞くことができました!
- 今回エンブレムを作ろうと思ったきっかけは何ですか?
-
2013年、福井厚生病院は30周年を迎えたのは、皆さんご存知だと思うんですが、
実はICTも設立10周年なんです。
なので、これを機に、ICTメンバーが自覚する”何か”がないかと考えたんです。 - メンバーの”自覚”とは
-


こちらが吉田さん。腕につけられたエンブレムに刺繍された”ICT”の文字が光ります。 ICTの任期は2年。
認定医や認定看護師、認定薬剤師などのコアメンバーといわれる人を中心に活動しているのですが、それ以外のメンバーは、自分がICTだということを公にしなければ「何もせず?なく?」任期を終了することも少なくありません。
しかし、このエンブレムを付けることで、ICTメンバーだとみんなに知ってもらうことになり、折に触れて「自分はICTメンバー」だと否が応でも自覚するっていうか、させられるっていうのが狙いなんです。―ICTの看板を背負うってことですね。
ええ。院内のスタッフ間には、「ICT=感染の専門家」という認識がありますからね。感染で困ったことがあると、まずはICTメンバーに相談します。
そんな時、このエンブレムをつけているからには、それなりの対応をしたいし、相手もそれを求めていると思うんですよね。だから、看板を背負っていくということは、自然と向上心も必要になってくるんじゃないでしょうか?でも、それが苦痛だとは思ってほしくないんですよね。 「スキルアップできるチャンス」ってとってもらいたいんですよ。
なので、勉強会のスタイルも昼食時間を利用したものにしたり、取り上げる話題もすごく身近なものをとりあげたりして、”楽しく”活動できる工夫もしています。―なるほど。エンブレムがプレッシャーになっては、逆効果ですもんね。それに苦痛だと思いながらの活動って、結局“やらされ感”が先行してしまい、向上心になかなか繋がらないですもんね。
- エンブレムの効果は感じていますか?
-
まだ始めたばかりなので、なんとも言えませんね。
でも、医師が先頭をきってエンブレムをつけてくれたことはすごく大きいです。やっぱり、医療のリーダーは医師ですからね。これから先、どんな効果を発揮してくれるか楽しみです。―小さなアクションが、大きな動きにつながるといいですね。そうなるためにもやっぱり、ICTメンバーの意識が変わることが第一歩なんでしょうね。
- このエンブレムを付けている人は何名いますか?
-
全員で29名です。
エンブレム1つ1つにナンバーがふられています。ちなみに僕は”7″。大好きなサッカーでいうところの中盤のポジションの番号です。いろんな意味で『繋ぎ』が役割りですね(笑)。―どんなに能力にたけたメンバーがそろっていても、繋ぎがしっかりしていなければ、チームとしての力が発揮できませんもんね。まさに『縁の下の力持ち』ですね。
- 最後に、ICTの“これから”をうかがえますか?
-
まだまだ、面白いことを考えていきたいと思います。目指すところは、情報共有と楽しい感染対策です。次のアクションをお楽しみに!
現在、コアメンバーとして精力的に活動している吉田さんも、前任のメンバーから引き継いだときは、感染症に関する知識はほとんどなく、ICTに関わるようになってから感染症に興味をもったそうです。
「知識や情報を身につければ、それが自信となり、発信や提案をすることができる。そのためにも、楽しく取り組むことが大事」だと話してくれた吉田さんの頭の中には、次なるアイデアが、すでに生まれているだろうなと感じました。